%20(720%20x%201080%20px)%20(720%20x%201040%20px)%20(720%20x%201020%20px)%20(700%20x%201000%20px)%20(1000%20x%20700%20px)%20(920%20%C3%97%20600%20px)%20(920%20%C3%97%20450%20px).png)
|
| 理事会議事 |
管理組合の理事をやってると「理事会」に出席しなければなりません。
総会は年1回必ずしなければなりません。
最近はコロナの影響もあり「書類による決議」も採用されているようですが、「集会によらない決議」とはどのようなものかイメージがつかない方もいるでしょう。
そもそも「総会議事録」とはどのようなものか、「理事会議事録との違いは?」なども知っておきたいことです。
今日は「議事録」について学習します。
CONTENTS
管理組合は毎年1回以上、総会を開催しなければなりません
そして、総会を開催した場合は総会議事録を作成しなければなりません(区分所有法42条1項、標準管理規約49条1項)。
総会議事録は、議長が作成しなければなりません(区分所有法42条1項、標準管理規約49条1項)。そして、総会の議事長は原則として理事長が務めることとされています(区分所有法41条、標準管理規約42条5項)。そのため、総会議事録の作成義務は理事長が負います。
決議結果については、通常は「賛成多数で承認された」「賛成〇名、反対〇名で承認された」等の記載で足りますが、建物の復旧決議、建替え決議の場合は、各区分所有者の賛否を記載する必要があります(区分所有法61条6項、62条8項)。つまり「名前」を記載しなければならないのです。
また、議事録には、議長及び総会に出席した区分所有者2名が署名押印する必要があるため、議事の最初に議事録署名人を決めておきます。
なお、議事録の署名押印は総会決議の有効要件ではなく、議事録上、議長及び出席区分所有者2名の署名押印を欠いていても総会決議は有効です(東京地裁平成20年4月11日判決、東京地裁平成26年7月10日判決)。
総会議事録に記載すべき内容は、『議事の経過の要領と結果』であり、これを記録することを要し、かつ、この記録があれば足ります。
議事の経過については、その要領(要約したもの)のみを記録することを要し、記載すべき事項は、以下のとおりです。総会の日時および場所
議事の結果、すなわち議案の採否や継続等の記録を必ず記録します。
管理組合としては、議事録や会計帳簿のみならず、会計帳簿の原資料の閲覧や写真撮影を認めるべきと思います。
なお、正当な理由がある場合とは、閲覧請求権が濫用的に行使された場合をいうとされており、あらかじめ周知されている閲覧時間を無視して早朝深夜等の不適当な時間に閲覧の請求がなされた場合、閲覧の必要がないのに連日執拗に閲覧の請求がなされた場合、嫌がらせのための閲覧請求であることが明らかな場合などがこれに当たると考えられています。
標準管理規約においては、総会議事録に関する規定が準用されており、理事長は、組合員または利害関係人の書面による請求があった場合は、理事会議事録を閲覧させなければならないものとされています(標準管理規約53条4項・49条3項)。なお、理事長は閲覧日時、場所等を指定できることも総会議事録の場合と同様です。
標準管理規約においては、理事長は、会計帳簿、什器備品帳簿、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があった場合は、閲覧させなければならないものとされています(標準管理規約64条1項)。
区分所有法には、総会の議事録の作成する義務が定められていますが、理事会議事録についての定めはありません。しかし、標準管理規約では、総会議事録に準じて理事会の議事録を作成するように規定されています。
仮に管理規約に、理事会議事録の作成についての記載がない場合でも、理事会での検討事項を記録として残すことは重要なことですので議事録は必ず作成するようにします。
議事録については、第49条(第4項を除く)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
確認事項
理事会の議事録作成で最も重要なことは審議の内容を正確に記載することです。次に迅速に議事録を作成した後に、コピーなどの配布をおこなって広報をすることです。理事会の活動や検討事項を、他の組合員に逐次周知することは、管理についての関心の向上につながります。
議事録は「管理に関する専門用語を用いること」や「体裁がよいこと」よりも、議事録の目的はあくまで記録として残すものですので、あまりこうした事に時間をとられるよりも正確に迅速に作成することが大切です。
また、理事会を開催した場合も理事会議事録を作成しなければなりません(標準管理規約53条4項)。
(1)総会議事録は理事長に作成義務がある
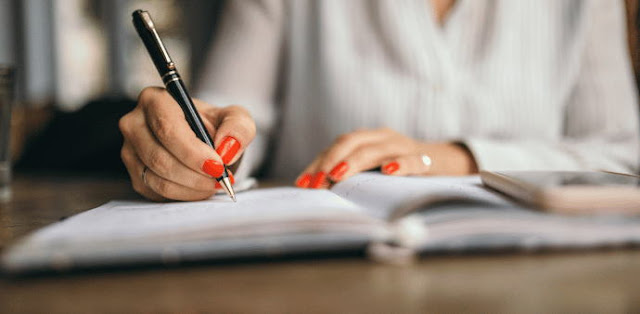 |
| 総会議事録 |
もっとも、実務上は書記等の担当者が原案を作成し、この原案に対して理事長を含む管理組合役員が確認修正を行うことを通じて作成します。
(2)総会議事録の作成方法
総会議事録は、書面または電磁的記録で作成します。「磁気ディスク、磁気テープ等のような磁気的方式によるもの、ICカード、ICメモリー等のような電子的方式によるもの、CD-Rのような光学的方式によるものなど」が挙げられています(標準管理規約49条関係コメント②)。(3)総会議事録の記載内容
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければなりません(区分所有法42条2項、標準管理規約49条2項)。
総会議事録の書式例は以下のとおりです。
総会議事録の書式例は以下のとおりです。
決議結果については、通常は「賛成多数で承認された」「賛成〇名、反対〇名で承認された」等の記載で足りますが、建物の復旧決議、建替え決議の場合は、各区分所有者の賛否を記載する必要があります(区分所有法61条6項、62条8項)。つまり「名前」を記載しなければならないのです。
また、議事録には、議長及び総会に出席した区分所有者2名が署名押印する必要があるため、議事の最初に議事録署名人を決めておきます。
なお、議事録の署名押印は総会決議の有効要件ではなく、議事録上、議長及び出席区分所有者2名の署名押印を欠いていても総会決議は有効です(東京地裁平成20年4月11日判決、東京地裁平成26年7月10日判決)。
議事録に記載する内容
総会議事録に記載すべき内容は、『議事の経過の要領と結果』であり、これを記録することを要し、かつ、この記録があれば足ります。
議事の経過については、その要領(要約したもの)のみを記録することを要し、記載すべき事項は、以下のとおりです。総会の日時および場所
- 議長の開会宣言
- 組合員総数、議決権総数、出席組合員数、出席議決権数(本人出席数、委任状による代理人出席数、議決権行使書面数)
- 議案の提出
- 議案についての説明の概要
- 質疑応答の重要なもの
- 議事運営の動議と結果
- 議案に対する動議と結果
- 議案の採決とその結果
- 議長の閉会宣言とその時刻
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなりません。
- 収支決算及び事業報告
- 収支予算及び事業計画
- 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
- 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
- 長期修繕計画の作成又は変更
- 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
- 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
- 修繕積立金の保管及び運用方法
- 第21条第2項に定める管理の実施
- 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
- 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
- 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
- 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
- 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
- その他管理組合の業務に関する重要事項
管理組合としては、議事録や会計帳簿のみならず、会計帳簿の原資料の閲覧や写真撮影を認めるべきと思います。
総会の議長は、総会議事録を作成しなければならず、仮に議事録に虚偽の記載をしたときは20万円以下の過料に処せられることになっています。ちなみに、過料とは、刑罰ではありません。過料の制裁を科する手続きは、刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。
(4)総会議事録の保管方法
総会議事録は議長が保管し、保管場所を見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法42条5項・33条1項3項、標準管理規約49条5項6項)。(5)総会議事録閲覧請求への対応
区分所有者または利害関係人から総会議事録の閲覧請求があった場合、理事長は総会議事録を閲覧させなければなりません(区分所有法42条5項・33条2項、標準管理規約49条5項)。ただし、理事長は閲覧について、相当の日時、場所等を指定することができます。(6)議事録に関する義務違反に対する制裁
理事長が議事録の作成義務、保管義務等に違反した場合、20万円以下の過料に処せられることとされています(区分所有法71条1号3号)。議事録の内容に虚偽記載等があった場合も同様です(区分所有法71条3号)。管理規約の閲覧請求があった場合
利害関係人から管理規約の閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法33条2項)。正当な理由なく閲覧を拒んだ場合には、20万円以下の過料に処するという罰則規定も設けられています(区分所有法71条2号)。そのため、管理規約の定めをもってしても、閲覧請求を一般的に制限することはできません。なお、正当な理由がある場合とは、閲覧請求権が濫用的に行使された場合をいうとされており、あらかじめ周知されている閲覧時間を無視して早朝深夜等の不適当な時間に閲覧の請求がなされた場合、閲覧の必要がないのに連日執拗に閲覧の請求がなされた場合、嫌がらせのための閲覧請求であることが明らかな場合などがこれに当たると考えられています。
理事会議事録の閲覧請求があった場合
理事会議事録については、区分所有法の定めはなく、閲覧請求の取扱いは管理規約の定めに委ねられています。標準管理規約においては、総会議事録に関する規定が準用されており、理事長は、組合員または利害関係人の書面による請求があった場合は、理事会議事録を閲覧させなければならないものとされています(標準管理規約53条4項・49条3項)。なお、理事長は閲覧日時、場所等を指定できることも総会議事録の場合と同様です。
会計帳簿等の閲覧請求があった場合
会計帳簿等についても、区分所有法の定めはなく、閲覧請求の取扱いは管理規約の定めに委ねられています。標準管理規約においては、理事長は、会計帳簿、什器備品帳簿、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があった場合は、閲覧させなければならないものとされています(標準管理規約64条1項)。
謄写請求は認められる?
会計帳簿等の閲覧請求については管理規約上に標準管理規約同様の規定がある場合に、閲覧に加えてコピー機による複写等まで認められるかですが、謄写請求が認められるかどうかは、管理規約が謄写請求権を認めているかどうかによるものと解されるとされており、何も規定がない場合は認められないものと考えられます(裁判例として東京高裁平成23年9月15日判決)。理事会議事録の作成手続
 |
| 議事録の作成 |
(1)基本的には総会議事録と同様
理事会議事録の作成手続については、基本的には総会議事録に関する標準管理規約の規定が準用されています(標準管理規約53条4項)。そのため、理事長に作成義務があること(51条3項参照)、書面または電磁的記録で作成すること、理事長が保管し、閲覧請求の対象となることなどは総会議事録と同様です。(2)総会議事録との相違点
理事会議事録については、議事録の保管場所を掲示する必要がありません(標準管理規約53条4項は49条6項を準用していません)。 また、理事会議事録に関しては区分所有法上に規定がなく(そもそも理事会に関する規定がありません)、総会議事録のような義務違反に対する制裁規定はありません。区分所有法には、総会の議事録の作成する義務が定められていますが、理事会議事録についての定めはありません。しかし、標準管理規約では、総会議事録に準じて理事会の議事録を作成するように規定されています。
仮に管理規約に、理事会議事録の作成についての記載がない場合でも、理事会での検討事項を記録として残すことは重要なことですので議事録は必ず作成するようにします。
標準管理規約(議事録の作成、保管等)
第49条- 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
- 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
標準管理規約(理事会の会議及び議事)
第53条(抜粋)議事録については、第49条(第4項を除く)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
確認事項
理事会の議事録の完成後の取扱い
議長の他2名、計3名の署名が終了した理事会議事録の原本は大切に保管します。また、議事録が完成した時点で、理事会からの広報として、管理組合毎のルールに応じて、コピーを掲示板に張り出したり配布するなどの対応をおこないます。
また、標準管理規約によれば、利害関係者から閲覧の申請があった場合には、議事録の閲覧に応じる必要があります。
理事会の議事録作成で最も重要なことは審議の内容を正確に記載することです。次に迅速に議事録を作成した後に、コピーなどの配布をおこなって広報をすることです。理事会の活動や検討事項を、他の組合員に逐次周知することは、管理についての関心の向上につながります。
議事録は「管理に関する専門用語を用いること」や「体裁がよいこと」よりも、議事録の目的はあくまで記録として残すものですので、あまりこうした事に時間をとられるよりも正確に迅速に作成することが大切です。





0 件のコメント:
コメントを投稿