地震による隣家の火事のもらい火で自宅が全焼することがあります。津波の後、火災が広がる場合もあります。人生の思い出の品が消失し失意の淵に立たされます。家を失えば転居を迫れ、費用がかさみ心労が重なります。
しかし、火災保険は適用されません。「地震や津波による損害は、保険金を払いません」という約款があるのです(地震免責)。まさかの時に火災保険は役に立ちません。損保代理店は「ライフライン」です。知り合いの代理店なら迅速な采配で恩恵を受け、その役割を実感します。
しかし、火災保険は適用されません。「地震や津波による損害は、保険金を払いません」という約款があるのです(地震免責)。まさかの時に火災保険は役に立ちません。損保代理店は「ライフライン」です。知り合いの代理店なら迅速な采配で恩恵を受け、その役割を実感します。
目次
1.県別で保険料に差がある
生活の土台となる住宅、終の棲家は安心して人生を過ごすために最も大切です。被災者が少しでも安心できる施設や場所の確保、緊急通報装置、火災警報器、自動消火器などの普及に、国、自治体、関係機関は全力を挙げることが求められます。
地震保険は火災保険とセットで加入する仕組みになっています。火災保険は入っていても地震保険までは・・・と迷っておられる方は、この保険の内容を知っておいたほうがよさそうです。
地震保険は県によって保険料に差があります。これが火災保険や自動車保険と大きく異なるところです。なぜ、保険料に差があるのでしょうか?
保険料が高い都道府県- 東京・神奈川・千葉・静岡
- 茨木・埼玉・愛知・三重・和歌山・大阪・徳島・愛媛・高知
- 上記以外
県によって3倍も料金が違うことに驚きます。自動車保険は過去の事故歴から料金が変わります。地震も国の地震予測にもとづいて算出されるのです。東京や神奈川など都市部は住宅も高いので被害額が大きくなります。
太平洋側の県で高いってことは「南海トラフ巨大地震」。地震発生のリスクが、保険料に現れているってことです。
2.地震保険に入るには、火災保険とセット
火災保険に加入していないと地震保険に入れない。火災保険に入っていても、そこと違う保険会社で地震保険を掛けることもできない。例外はあるのだろうが基本的にそういう決まりになっているようだ。
火災保険は建物の劣化した部分を差し引いた時価を基準に保険金が支払われるから、おなじような家を保険金だけでは再建できないこともある。再建の有無にかかわらず、建物や家財と同程度のものを新たに購入できるだけの保険金が支払われる「価額協定保険特約」がついているか確認する必要がある。
火災保険は建物の劣化した部分を差し引いた時価を基準に保険金が支払われるから、おなじような家を保険金だけでは再建できないこともある。再建の有無にかかわらず、建物や家財と同程度のものを新たに購入できるだけの保険金が支払われる「価額協定保険特約」がついているか確認する必要がある。
3.「県民共済」の地震保険はどうなの?
 |
都道府県民共済では、これまで地震による損害に対しても「新型火災共済」の共済金をお支払いすることでお役立ていただいてきました。大きな衝撃を与えた阪神淡路大地震、東日本大震災等々。以来地震保障への関心が高まり、より手厚い地震への備えを望む声が寄せられました。
そこでご加入者の皆様のご要望にお応えするために検討をかさね、このたび地震保障への改善を行います。さらに拡充した「新型火災共済」が暮らしの安心を守る力になります。【道府県民共済の地震保険】より引用
これまでは、全壊・半壊のみが保障の対象でしたが、20万円を超える半壊・半焼未満の損害(一部破損)についても、一律5万円の「地震等基本共済金」の対象となります。(加入金額が100万円以上の場合に限る)
特約、新登場
加入額2900万円の場合→木造:住宅と家財の合計)
2900万円×15%=435万円
掛け金
年払いーーー20880円
月払いーーー1827円
共済などの地震による損害は一時金や見舞金(10万円程度)といわれていましたが、半壊・半焼以上でも15%+5%=20%保障してもらえるようになりました。朗報です。
火災保険
火災や爆発、風水害・落雷など自然災害などから建物や家財道具を守る保険です。これが地震保険と関係するのです。火災保険は、地震・噴火・津波による損害は免責事項になっており補償の対象外。受け取れる保険金額は保険契約時と同等の住宅や家財を買いなおす費用を補償。
地震保険
火災保険で対応できない地震や噴火や津波などが対象。保険金額は火災保険の保険金額の30~50%で、建物は5000万円、家財は1000万円まで。被害の程度に応じて「全損」(保険金の100%)、「大半損」(60%)、「小半損」(30%)「一部損」(5%)の4段階。
阪神淡路大震災では、地震で起こった火災によって多くの住宅などが焼失したが、地震保険の加入率が低く、補償を受けられなかった。同じ火災でもその原因が地震かそうではないのかで対応する保険が違う。
火災保険と地震保険の両方に加入する事で、そんな災害からも建物・家財を守ることが出来る。地震が原因で起こった火災は、火災保険の免責事項に該当し保険金は一切支払われませんが、地震保険に加入していれば、地震保険から補償を受けることが出来るという事。
加入率は年々増加傾向でも3割程度に留まっているのが現状。火災保険に加入している方の半数以上は地震保険に加入している。加入率と付帯率共に2011年以降関心が高くなっている。
地震により建物の外壁にひび割れが生じ、その亀裂が5本ほど確認された。損害額は建物評価額の5%、一部損の認定。 自宅の階段が少し歪んだケース→一部損の認定
建物の地震保険は地震を起因とする損害が出た場合には、最低でも一部損の認定を受けやすい。 建物の評価額は火災保険などの評価額と損害額(修理見積り等)を比べて、その割合を見る。 大体どれぐらいの損害認定になるのが解る。
家財道具の主な損害は、食器類。どれだけの食器が割れたのかと言うのをヒアリングしながらの損害認定。テレビの液晶が割れた、その他家財道具すべて合わせて損害額がいくら、その割合によって損害程度が解ります。
4.保険料の目安
保険料は建物の所在地や構造などによって変わり、建築年や耐震等で割引もあります。
東京都の新築木造住宅で保険金を建物2000万円。家財500万円。
→43000円(1年一括))+地震保険=84000円くらい。
5.保険金支払い
- 小規模な損害であれば、損害額と同額かそれ以上の保険金を受け取れる可能性。
- 大損害は、損害額よりも受け取れる金額は少ない。
- 損害調査は、大規模災害で保険会社の調査員や社員が現場を見に来ることが多いが、地震発生後から数日から数週間、長ければ数か月来るまで時間がかかることがある。
- 家財道具を片付けては現物を見せられないので写真を撮っておく。
- 調査・審査は火災保険よりもゆるい傾向。
地震保険の保険料は、所得税・住民税の控除対象
・所得税:地震保険料の全額(最高50,000円)
・住民税:地震保険料の1/2(最高25,000円)
・所得税:地震保険料の全額(最高50,000円)
・住民税:地震保険料の1/2(最高25,000円)
保険料控除は現在地震保険料のみ。
長期積立火災保険は税法が変わる前の契約に限り、暫定的に控除を受けることは出来ます。
毎年10月、保険会社より地震保険料控除証明書が送付されます、年末調整または確定申告の時に使えるように保管しておいてください。
火災保険に加入して万全だと思っていても、地震で倒壊したり火事になって焼失した場合には全く補償は無い。加入していたからと言って、再建に必要な保険金が貰えるわけではありませんが、それでも再建するための金額の半分ほどの補償はあります。半分と言うのは有ると無いとでは大きな差です。
また、一般の火災保険は家屋と家財を別々に保障対象としているので注意しなければなりません。
また、地震保険に加入していても住宅ローンは残ってしまうので、自宅を再建しようとすると二重ローンになる。地震保険に加入していなければ、被災した時の当面の生活費なども困る。
まとめ
日本は地震国。もしもの時に困らないように地震保険。2011年以降地震保険の加入率・付帯率が全国的に高くなっています。宮城県・熊本県は全国的に見ても非常に高い。
自分が体験したことから地震保険の必要性を理解して加入している。
静岡や高知や徳島も非常に高い。災害に危機感。人は災害が起こった時には準備をしなければと思いますが、月日が経つとその思いや考え方は薄れていきます。月日がたてば災害の記憶も薄くなり、危機感は薄れていきます。
静岡や高知や徳島も非常に高い。災害に危機感。人は災害が起こった時には準備をしなければと思いますが、月日が経つとその思いや考え方は薄れていきます。月日がたてば災害の記憶も薄くなり、危機感は薄れていきます。
「備えあれば憂いなし」、その通りであり、地震に対する備えは保険でもしっかりと備えなければいけません。火災保険に比べて保険料は非常に高いが、その分、税金の控除対象になっている。12月になると申し込みが殺到するので余裕をもって対策を。
ファイナンシャルプランナーが30社全ての保険を扱うことのできる日本最大の保険代理店「保険見直しラボ」で無料相談をしてみるのがよいでしょう。
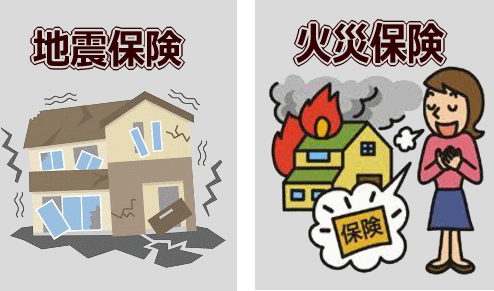

%20(720%20x%201080%20px)%20(720%20x%201040%20px)%20(720%20x%201020%20px)%20(700%20x%201000%20px)%20(1000%20x%20700%20px)%20(920%20%C3%97%20600%20px)%20(920%20%C3%97%20450%20px)%20(920%20%C3%97%20460%20px)%20(7).png)
%20(720%20x%201080%20px)%20(720%20x%201040%20px)%20(720%20x%201020%20px)%20(700%20x%201000%20px)%20(1000%20x%20700%20px)%20(920%20%C3%97%20600%20px)%20(920%20%C3%97%20450%20px)%20(920%20%C3%97%20460%20px)%20(8).png)




0 件のコメント:
コメントを投稿